2007年度 村松・野口スタジオ “継承の仕組み:京浜と共に生きる”

実際の設計に当たっては、デザインの質を重視すると同時に、何を再生するのかという柔軟な思索的プログラムを深く追求します。つまり、都市・建築のデザインの他にも、装置の都市的介入、外部の人々及び、地域住民の意識を再生するプログラムやアクティビティに関するエレガントな計画、そのデザインも期待しています。

京浜工業地帯では、90年代に起った産業構造の変動、グローバル経済の流れによって経済的なポテンシャルが弱まったために空洞化が進み、現在では再生・再整備が強く求められています。しかし、工業地帯における歴史的価値および文化的価値がいまだ明確に定義されていないために、地域環境に対する負のイメージが強く価値判断を左右し、それが再生する際のスタンスを決める大きな要因となっています。それ故、再生・再整備の提案においても積極的に工業地帯ならではの利点を活用していこうとするものよりも、如何にしてそのイメージを払拭できるかを模索しているものが多く見られます。また、工場地帯である事を積極的に取り入れようと試みているものでも、その地域の文脈や歴史を読み解いた上での提案は少なく、その手法は美術館や、公園等のお決まりのものが多いです。
本課題は、COEプログラムの成果を利用しつつ、このような工場地帯における現在の価値基準・再生手法を踏まえた上で、工業地帯とそれに伴う形で発展を遂げてきたその周辺地域において新しい価値を創出し、多様な視点、多様なスケールから今後の工業地帯の可能性を模索するものです。
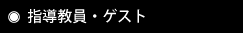
|
●指導
村松 伸
野口 貴文
●TA
新堀 学
六角 美瑠
三村 豊
望月 蓉平
●ゲストクリティク
藤森 照信
六角 鬼丈
国広 ジョージ
宮本 佳明
中谷 礼仁
松原 弘典
野原 卓
●講義
淺川 敏
山崎 博史
岩本 唯史
|
(東京大学生産技術研究所准教授、建築史家)
(准教授)
(新堀アトリエ一級建築事務所、建築家)
(東京藝術大学教育研究助手、建築家)
(村松研非常勤技術補佐員)
(村松研修士課程、大学院生)
(東京大学生産技術研究所教授、建築史家)
(東京芸術大学美術学部長、建築家)
(国士舘大学教授、建築活動家)
(大阪芸術大学環境デザイン学科助教授、建築家)
(早稲田大学建築学科准教授、歴史工学家)
(慶応大学SFC准教授、建築家)
(東京大学国際都市再生研究センター特任助手)
(ZOOM共同主宰、建築写真家)
(鹿島建設(株)建築設計本部)
(建築家)
|
 |
| 2007/4/17 講義 |
 |
| 2007/5/9 スタジオ内での中間発表 |
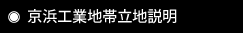
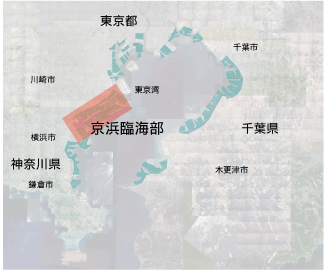 |
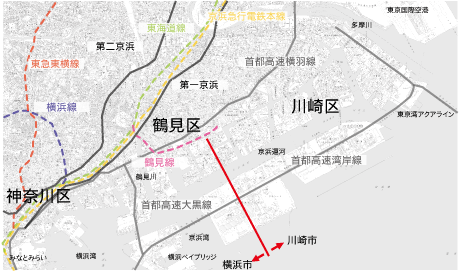 |
| 東京湾岸の京浜工業地帯(Google earthを用いて作成) |
京浜臨海部(国土交通省国土地理院の地図を用いて作成) |
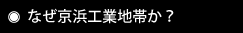
① 産業構造の転換期
② 未利用地の増加
③ 日本の工業地帯の中枢
④ 都市(地域)のもつ歴史遺産・資産の活用法
⑤ 活きた工場地帯再生のモデルとして
⑥ 持続再生学の都市展開
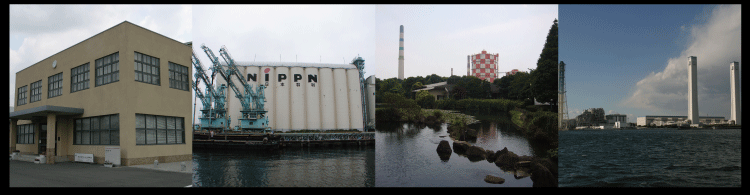 |
| 日産自動車横浜工場 |
日清製粉鶴見工場 |
JFEスチール扇島 |
東京火力発電所トゥイニー横浜 |
 |
| 東芝横浜工場 |
弁天橋駅 |
新日本石油横浜製油所 |
新興線(廃線) |
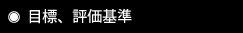
1)現状を、自分の眼と自分の足で観察する。
2)独自で鋭く斬新な問題を発見する。
3)柔軟な発想を総動員する。
4)現状のある側面を継承する。
5)学を融合し、深く体系的な思索をする。
6)エレガントな操作を施す。
7)未来のためにゆたかで、細部まで設計された空間を創造する。
8)的確で魅力的に表現する。 |
〔フィールドワーク〕
〔フレーミング〕
〔フレキシビリティ〕
〔目的〕
〔学問の融合性〕
〔コンセプト〕
〔設計の到達度〕
〔プレゼンテーション〕 |
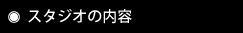
・フィールドワーク(全体、個人)
・講義
・文献収集、分析
・全体エスキス
・グループエスキス
・個人エスキス
・専門家からのアドバイス
・全体講評

4/10 キックオフ
4/17 敷地と工業遺産について理解する
4/25 フィールドワーク
5/01 ブレーンストーミング(1)
5/02 ブレーンストーミング(2)
5/09 計画案の提示(講評会)
5/15 中間講評
5/22 設計案の提示(個人エスキス)
5/29 設計案の提示(講義、個人エスキス)
6/06 設計案の提示(講評会)
6/12 設計案の提示(グループエスキス)
6/13 設計案の提示(個人エスキス)
6/19 提出前、スタジオ講評会
6 26 展示、第一次講評
7/03 第2次講評
7/04 村松・野口スタジオ講評会、うちあげ
|

|